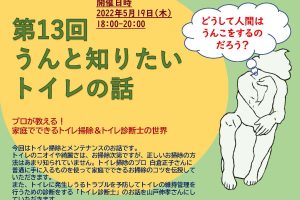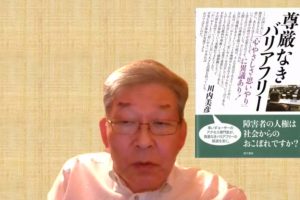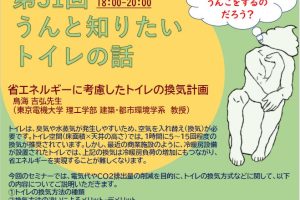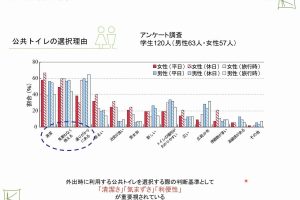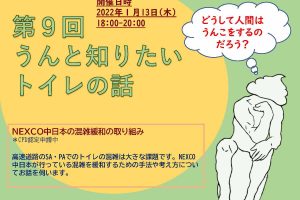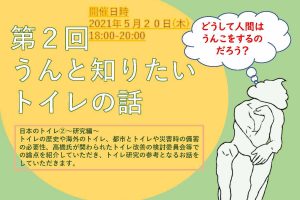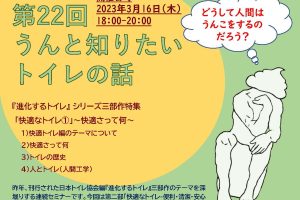JTAトイレ賞受賞作品から Part1
司会・講師
- <講師1>「六甲最高峰トイレ」 小原賢一、深川礼子(株式会社ofa)
- <講師2>「公民連携!みんなで創った、みんなにやさしい新庁舎トイレ」 馬場裕子(長崎市)、竹中晴美(みんなにやさしいトイレ会議)
- <司会>高橋未樹子 日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長
講演概要
(司会:高橋)
皆さま、ご参加いただきましてありがとうございます。時間になりましたので、第38回「うんと知りたいトイレの話」を始めさせていただきます。本日の進行を務めます、トイレ協会の高橋です。今回は2023年度のJTAトイレ賞で受賞された二つの作品にご講演いただきます。一つ目は株式会社ofaの小原さんから、2021年に六甲山エリアに新設された山のトイレについて、自然環境との調和や環境配慮の取り組みをご紹介いただきます。二つ目は長崎市の馬場さんと、市民ボランティア活動として公衆トイレの改善に取り組んでこられた竹中さんに、市民の小さな声も取り入れて細かな配慮がされた長崎市の新庁舎トイレについてお話いただきます。
それでは、発表の前にJTAトイレ賞の紹介をトイレ協会の浅井さんから5分程度お願いいたします。
(浅井)
JTAトイレ賞委員会の浅井です。JTAトイレ賞について、経緯と内容を簡単にご説明します。この賞は、みんながいつでもどこでも気持ちよく使えるトイレ環境を作り、それを持続できる社会をつくることを目標に、顕著な活動を実践・提案している方を表彰するものです。その歴史は古く、トイレ協会が発足した1985年に「グッドトイレ10(テン)」として始まりました。当時は主に公共トイレの良い事例を選び、皆様に知っていただくことで全体の環境改善を目指していました。その後、ハードの建物だけでなく、メンテナンスやソフト面での活動も評価の対象とするため「トイレ選奨」となり、さらに2021年からは内容の多岐化に対応するため、「A:作品部門」「B:著作・研究部門」「C:維持・管理・運営部門」「D:社会的活動部門」の4部門に分けました。そして、これらの見直しを経て、昨年2023年度から「JTAトイレ賞」という現在の名称になりました。賞には各部門の「JTAトイレ賞」のほか、特に優れたものに贈られる「大賞」、そして「奨励賞」や「学生賞」といった特別賞も設けています。また、審査員だけでなく、トイレシンポジウムの来場者による一般投票で決まる「一般投票賞」もあります。受賞されますと、表彰状が授与されるだけでなく、トイレに関わる専門家からの評価を得られ、協会ホームページや新聞、専門誌などで広く公開される機会も広がります。本日の発表も、受賞された方々がどのような取り組みをされているかを知っていただく良い機会ですので、ぜひ今後の応募の参考にしていただければと思います。
六甲最高峰トイレ
(司会:高橋)
ありがとうございます。では早速、一つ目の発表、六甲最高峰トイレについて株式会社ofaの小原賢一さんからお話をしていただきたいと思います。こちらの作品は作品部門で奨励賞を受賞されました。審査員からは「山並みや樹冠の連なりを感じさせるCLTパネル屋根の下、快適な空間がデザインされている」「地域の木材を用い、上下水道のない立地での雨水や循環水、自然光や自然換気などサスティナビリティへの配慮とコンセプトがよく合っている」とのコメントをいただいています。それでは小原さん、よろしくお願いいたします。
(小原)
本日はありがとうございます。受賞した六甲最高峰トイレについてお話させていただきます。私たちの事務所は神戸の六甲山の麓にあり、私と深川の2名で運営しています。まず、六甲最高峰トイレは、六甲山の自然に調和する折れ屋根とクサハラで作るレストスペースとして計画しました。この場所は六甲山の山頂に近く、ハイキングコースの途中に位置し、多い日には1日に2000人が通行する場所ですが、上下水道が未整備な場所です。そこに、メンテナンスの手間が少なく快適なトイレを作ることが課題でした。計画前の敷地はただの砂利敷きの平場で、特に休憩する場所もありませんでした。そこで、人と自然のバランスを整え、持続可能性と魅力創出を両立するデザインを目指しました。具体的には、タニ状の折れ屋根で雨水を集めて手洗いに利用し、汚水は土壌微生物膜浄化槽で浄化し、トイレ洗浄水に再利用するシステムを導入しました。建築のコンセプトは、風と光が通る、家具のようなトイレです。大きな庇の下にトイレの箱を家具のように配置し、壁を斜めにしてゆったりと座れるベンチを設けました。トイレブースは中央に固めて回遊動線を確保し、安全性を高めるとともに、冬の厳しい寒さから便器を守る役割も果たしています。木材は、屋根に兵庫県産材のヒノキ・杉のCLTパネルを、外装の一部には六甲山系の間伐材を利用しました。建築だけでなく、在来種の草を植えた「クサハラ」の広場をランドスケープとして一体的に整備し、植栽のワークショップも行いました。訪れた人が思い思いの場所で休憩できる、気持ちのいい場所ができたと感じています。
(司会:高橋)
小原さん、ありがとうございました。山にあるとは思えない綺麗なトイレで驚きました。質問をいただいております。まず、トイレ協会の山本耕平会長からです。「雨水貯留槽の容量はどれぐらいですか。雨水だけでこの規模のトイレの水を賄えますか」というご質問です。
(小原)
雨水貯留槽は5トンです。設計時に利用人数などを計算して決めているので、基本的には賄える想定です。もちろん、長期間雨が降らなければ足りなくなる可能性はありますが、その際は渇水警報が出て給水車で運ぶ仕組みになっています。今のところ、頻繁に渇水しているとは聞いていません。
(司会:高橋)
ありがとうございます。次の質問です。「登山客が利用するトイレなので、靴を洗う方もいるかと思います。衛生面や清掃のしやすさで気をつけたことはありますか」。
(小原)
トイレの中の床は、水が溜まってカビが生えるのを防ぐため、基本的に乾式清掃としています。靴を洗う専用の場所は設けていません。登山道からの泥汚れは、週に一度、掃き掃除をメインに清掃していただいています。
(司会:高橋)
続いて、白倉さんから質問をいただいております。「浄化槽は、汚泥の汲み取りはするのですか」と「水が減るとセンサーで知らせがあるようですが、どこに届くのですか」という二つの質問です。
(小原)
浄化槽については、まず地下に1次処理槽のタンクがあり、そこで溶けないゴミを溜めています。そのゴミはマンホールを開けて人が取り除いています。溶けるものはそのまま土の中に浸潤していく仕組みです。センサーの知らせは、ここから離れた場所にある森林事務所に飛ぶようにしています。Wi-Fiを設置しており、それで通知が飛ぶようになっています。
(司会:高橋)
ありがとうございます。もう一点質問です。「中央の多目的トイレは2室でしょうか」。
(小原)
中央の多目的トイレは一つです。その隣のスペースは、浄化槽や雨水循環のための機械室になっています。多目的トイレには簡易オストメイトやベビーシートも設置しています。
公民連携!みんなで創った、みんなにやさしい新庁舎トイレ
(司会:高橋)
ありがとうございました。では次に、長崎市の新庁舎トイレについて、「みんなにやさしいトイレ会議」の竹中晴美さんと長崎市の馬場裕子さんにお話していただきます。こちらの作品は社会的活動部門でJTA賞を受賞されました。審査員からは「12回にも及ぶ市民・利用者が参加した話し合いの成果が結実した、みんなで創ったトイレである」「公共施設作りへの市民参加のモデルとしても高く評価できる」とのコメントです。では竹中さんからお願いいたします。
(竹中)
ありがとうございます。「みんなにやさしいトイレ会議」の竹中です。この取り組みは14年間、市役所と一緒にやってきたことの集大成です。活動のきっかけは35年前、私が企画した女性が主役の街歩きでした。当時、トイレは汚いのが当たり前でしたが、街歩きにはトイレが必須だと考え調査を行い、その無残な実態をレポートで市役所に提出したのが、行政との最初の付き合いでした。その後、「一人で熱くなっても駄目だよ」という当時の市長の言葉をきっかけに、2010年、「使う側」「設置する側(行政)」「専門家」の三つの視点で取り組む「みんなにやさしいトイレ会議」を発足させました。私たちは「トイレ=まちづくり」をテーマに、洗面台のバッグかけ、多目的トイレのフックやベンチの設置といった具体的な改善提案を行ってきました。特に、自己導尿患者の方がカテーテルを置く場所に困っていると聞き、長崎大学の先生と勉強を重ね、カテーテルを装着しやすい「前広便座」と、その存在を示すCICマークを導入しました。こうした活動を設計図の段階から行政と話し合いながら実現できたこと、そして14年間の積み重ねで、行政内で担当者が異動してもきちんと引き継ぎがなされる信頼関係ができたことが、何よりの財産だと思っています。
(馬場)
長崎市役所の馬場です。新庁舎は令和5年1月に開庁しました。建設にあたり、「みんなにやさしいトイレ会議」の皆さまをはじめ、子育て団体や障害者団体など多くの方と延べ12回の意見交換を行いました。皆様からのご提案で、玄関からすぐ見える位置へのトイレ配置、お子様による誤開錠を防ぐための二重ロック、男性用小便器横のフック、全身が映る姿見などを標準で設置しました。また、公共施設にありがちな白い内装ではなく、気持ちが明るくなるようなパステルカラーのドアを採用しました。これは、設計業者から提案されたパンフレットを見て、私が温かいトイレにしたいと強く希望したものです。特にバリアフリートイレは、モックアップ(実物大模型)やVRで検証を重ね、視覚障害のある方のために壁と手すりの色にコントラストをつけたり、実際に座って荷物を取りやすい位置にフックを設置したりと、細かく調整しました。戸当たりの帽子掛けも、背の低い方でも使いやすいように、当初の設計より高さを下げています。誰もが使いやすいよう、今後もいただいたご意見を大切にしていきたいです。
(司会:高橋)
ありがとうございました。12回も会議を重ねるのは本当に大変だったと思います。質問が来ております。「ジェンダーレス対応のトイレを東側だけにした理由はありますか」。
(馬場)
ジェンダーレスの方は健常者に見えることがあり、そうした方が障害者向けの優先トイレに入っていると、苦情が出たり喧嘩になったりするというご意見を障害者団体の方からいただきました。そのため、東側は誰でも使えるトイレ、南側は障害のある方などが優先的に使えるトイレ、という形で機能を分けました。ただ、「絶対に使っては駄目」ということではなく、柔らかい表現として「優先トイレ」という名称にしています。
(司官:高橋)
次の質問です。「女性の街歩きから始まったとのことですが、男性トイレでの細かな配慮はありますか」。
(竹中)
男性だってショルダーバッグを持っているよね、ということで小便器の横にフックをつけましたが、今では杖や傘をかけるのに便利だと大変喜ばれています。また、男性はコートを脱いでから個室に入ることが多いと聞き、コートが床にすれない高い位置にもフックを設置しました。男女でこんなに使い方が違うのかと、長年の調査で学びました。
(馬場)
男性用個室も、荷物が置けるよう女性トイレと同じぐらいのスペースを確保できるよう、ライニング(便器背後のスペース)の広さも考えて作っております。
(司会:高橋)
最後に、「市民の声を聞く際にどのような工夫が必要ですか。異なる意見をどうまとめていますか」という質問です。
(馬場)
図面は専門的なものをそのままお見せするのではなく、簡易なものに作り直してお見せしました。また、採用できないご意見については、その理由をきちんとご説明しました。各団体と1回で終わらせずに、何度も対話を重ねることで、皆様にご納得いただけるようお願いしました。結果として、反対意見というよりは、取り入れてほしいという良いご意見をたくさんいただけたので、うまく反映できたと思っています。
(司会:高橋)
ありがとうございました。お二人のご発表を終わりにしたいと思います。お話を伺い、トイレに対する情熱に毎回刺激を受けています。皆さまもぜひ今年のJTAトイレ賞にご応募ください。本日はありがとうございました。