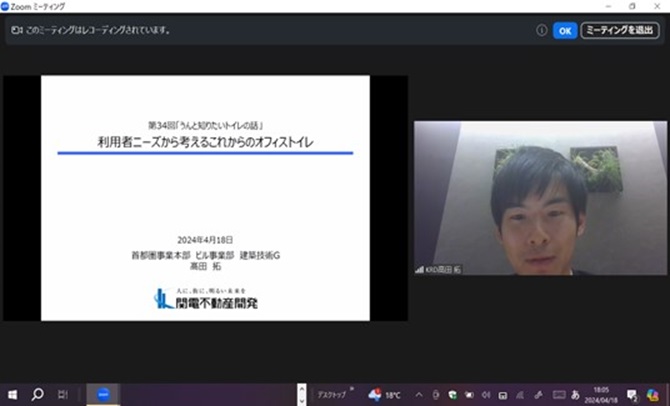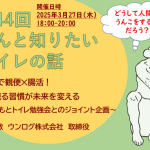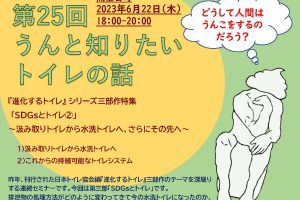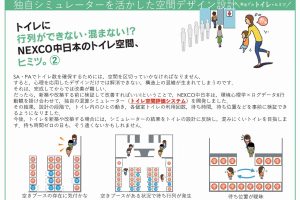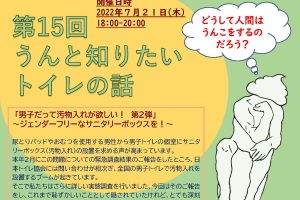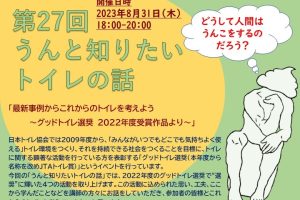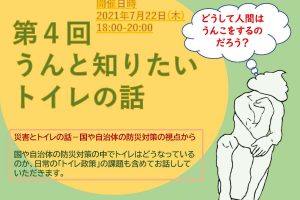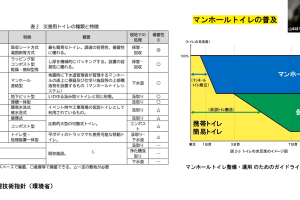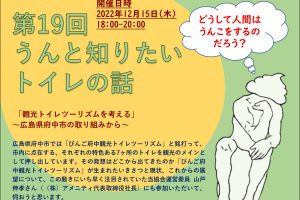- 司会
- 高橋未樹子 日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長
- 講師
- 髙田拓(関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部ビル事業部建築技術G チーフリーダー)
講演概要
(高橋)
本日は第34回「うんと知りたいトイレの話」を開催いたします.テーマは「利用者ニーズから考えるこれからのオフィストイレ」です.関電不動産開発株式会社の髙田様をお招きし,ご講演いただきます.高田様の活動は2023年度のJTAトイレ賞で奨励賞を受章されました.審査員の小松先生と長澤先生からは,高い評価のコメントを頂戴しています.
高田様のお話
本日は,弊社の八重洲ビルのトイレを中心に,利用者ニーズから考えるこれからのオフィストイレについてお話しさせていただきます.
まず,関電不動産八重洲ビルの概要からご説明いたします.当ビルは東京駅から徒歩約10分の場所に位置する,地上13階建て,延床面積約1万3千平米の中規模オフィスビルでございます.2022年5月に竣工し,1階にはコンビニエンスストアを設けておりますが,主な用途はオフィスとなっております.テナント企業様の入居工事を経て,実際にお客様に使っていただき始めてから1年が経過した段階でございます.
当ビルの特徴として,大きく二つ挙げさせていただきます.一つ目は,オフィスキッチンの設置です.従来,オフィスの水回りといえば,廊下の一角にある給湯室が一般的でございました.しかし当ビルでは,テナント企業様内外のコミュニケーション促進のしかけとして,執務スペースに隣接する形で専用部内にキッチンを配置いたしました.二つ目の特徴が,屋上に設けた約250平米程度のテラス空間でございます.こちらもテナント企業様の垣根を越えた交流の場としてご活用いただいております.
当ビルの開発コンセプトとしましては,大きく3点ございます.1点目が「働き方提案型オフィス」です.計画時の2018年頃は,コロナ禍以前でしたが,既に働き方改革が叫ばれ始めた時期でもあり,これからのオフィスのあり方を模索した次第でございます.2点目が「省エネ・環境への取り組み」,3点目が「BCP(事業継続計画)対策の充実」です.その中でも特に「働き方提案型オフィス」においては,先ほど申し上げましたオフィスキッチンやテラスに加えて,もう一つ大きな軸としているのが「多様性への配慮」です.健康状態,性別,国籍,宗教など,様々な多様性に配慮したオフィス,そしてトイレを作ろうと取り組んだのが当ビルの特徴でございます.
ここからは,オフィスフロア,つまり基準階のトイレについてご説明いたします.基準階は約250坪の面積で,エレベーターを中心に左右に男女別のトイレを配置しております.女性トイレは多機能を意識した設計で,3つの便器と3つの洗面に加えて,パウダースペースを2種類(カウンタータイプとドレッサータイプ),歯磨き用のボウル,更衣室,そして個人ロッカーのプライベートBOXを設けております.
一方の男性トイレも,洗面,小便器,大便器に加え,プライベートBOXと歯磨きボウルを設置いたしました.歯磨きをする男性も増えてきておりますので,手洗いと歯磨きがかち合わないよう配慮したのが特徴でございます.
女性トイレがこのようなレイアウトになった背景には,企画当初の検討プロセスがございます.快適性を重視し,混雑緩和,歯磨き,メイク,着替えなどの多様なニーズに応えるトイレを目指したのですが,特に悩ましかったのが,メイクスペースをどのように設けるかという点でした.トイレとは別の空間にするのか,トイレ内に設けるのか.また更衣スペースは本当に必要なのか,フィッティングボードで代用できるのではないか,といった議論もありました.検討を重ねた結果,何パターンものプランを作成したのですが,実際に利用される方々の声を直接聞こうと,テナント企業様の窓口となる方々にヒアリングを実施いたしました.
他ビルの事例も参考にしつつ,率直なご意見を伺った結果,フィッティングボードは使いづらい,パウダーは洗面と離れているより一体型が良い,カバンを置くスペースが欲しいなど,貴重なご意見を数多くいただきました.特にメイク直しは,他人の目を気にせずゆっくりできる空間が好まれること,出社時や外出前にトイレに立ち寄るという動線も見えてまいりました.
これらのご意見を踏まえ,最終的に採用したのが先ほどご覧いただいたプランです.洗面とパウダーを一体の空間とすることで混雑時にはどちらかを選べるよう十分な広さを確保し、カバンを置けるようにしました.フィッティングボードではなく更衣室を設け,トイレブースが足らない場合はトイレに変更できる設えとしました。男性トイレにもプライベートBOXを設置したのは,歯磨きグッズなどを収納するニーズがあったからでございます.
もう一つ,当ビルの新しい取り組みとして,1階に設けた「Restroom+」がございます.これは男女共用の個室型トイレで,2ヶ所に設置しております.車椅子対応トイレは別に設けた上で,「Restroom+」は広めの個室トイレとし,メイク直しや着替えもできる設えとしています.
きっかけは,先ほど申し上げた「多様性」への配慮でございます.性的マイノリティの方など,何らかの理由でオフィスフロアのトイレが使いづらい方のニーズに応える狙いがあります.LIXIL様と虹色ダイバーシティ様が実施した調査によると,「もし自由に選べるなら男女別トイレを使う」と回答した性的マイノリティ当事者は約半数で,「誰でもトイレを使いたい」と回答した当事者は約3割でした.この調査結果から,オフィスの男女別トイレが使いにくい方々がいらっしゃることが分かったので,当ビルでは,カフェやコンビニのトイレのようにストレスなく使える空間を目指しました.1階のメインストリートに面した場所に設け,入居者限定ではありますが,セキュリティゲートで管理することで安心感も担保しています.
名称の「Restroom+」には,「オフィスフロアのトイレ以上の機能」「働く人のパフォーマンスがプラスになる」といった想いを込めております.サインの工夫で男女共用であることをわかりやすく伝えるようにいたしました.
さて,ここからは実際の利用者アンケートの結果をご紹介いたします.まず,トイレの快適性は仕事のモチベーションに影響するかという問いには,実に7割近くの方が影響すると回答されました.トイレは単なる用足し以上の意味を持っているようです.では,具体的にどのような使い方をされているのでしょうか.上位は「ボーっと一休みする」「心を落ち着ける」などメンタル面でのリフレッシュ,また「体を伸ばす・ストレッチ」といった身体的な休息です.トイレが気分転換や休憩の場としても活用されている様子が浮かび上がりました.「スマホを触る」という回答も一定数ございました.
では,なぜトイレでそうした行為をするのでしょうか.最大の理由は「トイレが1人になれる場所だから」と思われます.家族がいる自宅でもオフィスでもなく,1人になれる貴重な空間がトイレです.周囲の目を気にせず,自分だけの時間を過ごせる場所であり、まだまだ潜在的なニーズに応える工夫が求められていると感じました.
続いて,ハンドドライヤーに関する設問です.コロナ禍で紙タオルに切り替えた方が多いのではという想定どおり,毎回使う方は2割以下と少なく、「使わない」と回答された方の半数以上が「ペーパータオル、ハンカチで代用する」「感染症が気になる」という理由でした。コロナ禍の数年間で習慣が変わったという面も踏まえて今後は計画する必要があるとアンケート結果から感じました.
Restroom+の利用状況についても調査いたしました.男女ともに約40%がこれまでに利用したことがあり,1日平均60回ほどの利用があるようです.利用目的としては「身だしなみを整える」が最多で,化粧やスキンケアをする男性が増えてきていることもあるかもしれません.興味深かったのが,内装デザインの好みが男女で分かれた点.シックな「LUXURY」は男性に,明るい「NATURAL」は女性に好まれる傾向が見られました.同じトイレでも,男女で求めるイメージが異なるのかもしれません.
一方で臭いや衛生面への不安,鍵をかけ忘れたままで使うといった課題も見えてまいりました.いただいた意見を踏まえ、ニオイ対策として消臭アロマの設置や清掃頻度を上げました.また鍵の位置を強調するサインの工夫など運用面の改善も図っております.こうした学びを生かし,今年2月に竣工した「関電不動産渋谷ビル」でもRestroom+を進化させた形で導入いたしました.便器と洗面・パウダーの距離を取る,ニオイ対策,便座の自動開閉,在室サインの設置など,利用者目線に立った改良を重ねております.
Restroom+については,まだ改善の余地があると考えています.
さて,この後,皆様に簡単なアンケートにご協力をいただきたいと考えています.
この趣旨としましては,私も,また次のトイレがどういったトイレが良いかなということを考える上で,皆様の中でトイレに対して感じられているものがあるのであれば,その部分を教えていただきたいという意図でございます.そんなに難しい内容ではないです.
まず,皆様がトイレって用を足す以外で使っていますか,それってどういった行為ですか.どこでやりますか.なんでそれをトイレでするのですか,そのぐらいの内容になっています.
あとは,実際に今のトイレに,何か不満を感じられていますかというあたりですね,そのストレスってどういったことですかというのをお聞きできればと思っています.
実はこういう使い方をされていて,ここって,課題なのですよねと思うことがあるとか,今回トイレは,特に個室ブースっていうのは,壁に囲まれた空間,こもれる空間ということで,何か1人でいろんなアクティビティをされるがいらっしゃる中,今って,こういうことをやっていますよ,みたいな,そんな情報があればぜひ,意見交換ができればいいなと思っているところです.
質疑
(高橋)
高田様のアンケートの結果を共有いたします.オフィスのトイレを,用を足す以外の目的で使用していると回答した方が全体の66.7%に上りました.ボーっと一休みする,心を落ち着ける,体を伸ばすなど,リラックス目的で個室ブースを活用しているケースが目立ちます.こうした行為をトイレで行う理由は,「1人になれるから」「自宅でもオフィスでもしにくいから」などが挙げられています.高田様,トイレが用を足す以外の多彩な用途で頻繁に利用されているという結果について,率直なご感想をお聞かせください.
(高田様)
利用実態の調査を通して,トイレが単なる排泄の場ではなく,頭や体を休める目的で活用されている実情が浮き彫りになりました.気軽に利用できる個室空間として,トイレがオフィスワーカーの皆様にとって貴重な存在になっているのだと実感しています.利用者のニーズを踏まえて,リラクゼーション効果のある設えを個室ブースに施していくのも一案かもしれません.一方で,本来はトイレとは別に,気兼ねなく休憩ができる場所を確保するのが望ましい形だとも考えていますが、設けられたリフレッシュスペースはサボってるみたいでなんだか利用しにくいといった実態があるかもしれません.
(高橋)
なるほど.専用の休憩スペースを設けたとしても,ついつい利用しづらさを感じてしまうのは確かにありそうですね.利便性の高いトイレ空間だからこそ,休憩目的でも重宝されているのかもしれません.トイレの在り方を考える上で,示唆に富むご指摘だと思います.会場のKA先生から,車いす用トイレの方がリラックスに適しているのではというご質問が寄せられています.一般ブースと比べて,車いす用トイレを休憩目的で使用することに対する心理的ハードルについて,高田様のお考えをお聞かせください.
(高田様)
ご指摘の通り,車いす用トイレは広々とした空間が確保されているため,一見するとリラックスに適しているようにも思えます.しかし,そもそも車いす利用者など,特定の利用者のために設けられた場所であるという認識から,そこを休憩目的で占有することに心理的な抵抗を感じる方は少なくないのではないでしょうか.必要としている人のための大切なスペースを,安易に別の用途に転用してしまうことへの罪悪感が,くつろぐ気持ちを阻害してしまう可能性もあります.そういった意味では,一般ブースの方が気兼ねなく利用できるというご意見には納得させられる部分があります.
(高橋)
車いす用トイレの利用に心理的なためらいを感じるという声は,私もよく耳にします.本来の目的に叶った形で活用してもらうためにも,周囲の理解を深める啓発活動が大切だと改めて感じました.さて,男子トイレの個室数について,フロアの参加者から質問が寄せられています.八重洲ビルの男子トイレでは,小便器と同数の大便器を設置されているそうですが,これは最近の傾向なのでしょうか.また,その狙いについて教えてください.
(高田様)
八重洲ビルでは,立地特性を踏まえて男性利用者の割合が高いと想定されたため,大便器の数を意図的に多めに設定しているように見えたかもしれません.ただ昨今は個室での用足しを好む男性利用者のニーズがあったり,オフィスの男女比も多様になっているので適切な器具数の考え方も見直す必要があるとは考えています.
(高橋)
大変興味深いお話でした.大便器の適切な数は,オフィスを取り巻く状況に応じて柔軟に変えていく必要がありそうですね.個室数の確保はもちろん,プライバシーや快適性にも十分に配慮していく視点が欠かせません.高田様,オフィスワーカーの皆様との対話の中で,トイレに関するどのような意見が印象に残っていますか.差し支えない範囲で,具体的なエピソードをお聞かせいただけますでしょうか.
(高田様)
オフィスの皆様からは,トイレの清掃とメンテナンスに関する声を多数いただきました.中でも気になったのは,清掃スタッフの方が作業に入っているタイミングで,利用者との鉢合わせが発生しているというご指摘です.混雑する時間帯を避けて清掃の時間割を設定するなど,利用状況に合わせた柔軟な運用体制の構築が求められていると実感しました.トイレが快適であり続けるためには,ハード面の充実はもちろん,管理面での工夫も欠かせません.
(高橋)
清掃タイミングと利用者の動線が輻輳するケースへの対処は,運用改善に向けた重要な示唆になりそうです.トイレ空間の快適性を維持する上で,ソフト面からのアプローチも欠かせませんね.高田様のお話からは,一人ひとりの利用者の声に真摯に耳を傾け,トイレ環境の向上に取り組んでいく真摯な姿勢が伝わってまいりました.些細なことのようでも,利用者にとっては切実な問題.オフィスで働く皆様が,より快適にトイレを使っていただけるよう,ハード・ソフト両面からの地道な努力を重ねていくことが何より大切だと,改めて認識を新たにした次第です.他にも,多数の質問が寄せられています.KAさんから,メンテナンス面で機器メーカーに対するご要望をお聞きしたいというご質問です.高田様,いかがでしょうか.
(高田様)
トイレ機器のメーカー様には,清掃スタッフの人手不足を見据えた製品開発に一層注力していただきたいと思います.利用者マナーの向上に依るところも大きいのですが,汚れやすい・掃除がしにくいデザインについては,何とか改善の余地がないかと感じています.例えば,床に飛び散った尿の処理.これは日常的に発生している光景ですが,従来の清掃用具では対処しきれない難しさがあります.床面の仕上げ方や,適切な清掃道具の開発など,メーカー様とのタッグによる技術的なブレイクスルーが望まれます.もちろん,節水性や使い勝手の良さなど,トイレ機器本来の性能追求も大切です.メンテナンスのしやすさとのバランスを取りながら,利用者にも清掃する側にもストレスのない,トータルな製品設計を期待しています.ビルオーナー,設計者,メーカーが一丸となって知恵を出し合い,快適なトイレ空間の実現に向けて協働していければと思います.
(KAさん)
高田様,示唆に富むご指摘をありがとうございます.おっしゃる通り,トイレ機器の開発に際しては,メンテナンス性への配慮が不可欠です.清掃スタッフの負担軽減につながるような工夫を施しながら,同時に利用者の満足度も追求していく.そのバランス感覚が問われていると痛感しました.現場の声に真摯に向き合い,一つひとつ課題解決に取り組んでまいります.本日は貴重なご意見を賜り,誠にありがとうございました.
(高橋)
トイレ機器の開発とメンテナンスの接点については,本日の議論で多くの示唆を得ることができました.利用者と清掃スタッフ,双方の視点に立った製品設計が,より快適なトイレ空間の実現に直結する.その重要性を再認識した次第です.続いて,KA先生から,男性トイレにおけるサニタリーボックスの設置について質問が寄せられています.オストメイトの方をはじめ,さまざまな利用者に配慮した環境整備の必要性について,高田様のお考えをお聞かせください.
(高田様)
ご指摘の通り,男性トイレにおけるサニタリーボックスの設置は,今後ますます重要性を増すテーマだと認識しています.誰もが抵抗なく利用できる環境整備は,喫緊の課題と言えますが、弊社では残念ながら,現時点で男性トイレへのサニタリーボックス設置は十分に進んでいません.しかし今後は,個室の数を確保した上で,備品面での配慮も積極的に行っていきたいと考えています.体調面の不安を抱えながら日々オフィスに通う方々が,安心して働ける環境.その実現に向けて,トイレ空間の在り方を問い直していく必要性を強く感じました.
(高橋)
誠にありがとうございます.トイレが多様な利用者のニーズに応えていくためには,一人ひとりに寄り添った,キメ細やかな配慮が欠かせません.サニタリーボックスひとつ取っても,実は男性トイレでの需要は想像以上に大きい.今回の議論を通して,改めてその重要性を認識することができました.一方で,機能面の充実と,現場での運用負荷とのバランスをどう取っていくか.これは設計者のみならず,ビル管理者にとっても難しい課題ですね.利用者の視点に立ち,知恵を絞りながら,地道に改善を積み重ねていく.そうした努力の先に,誰もが心地よく利用できるトイレ空間が実現できるのだと信じています.
HOさんから,意見と質問をいただいています.「トイレで用を足す際,知らない人がいない方が落ち着く」というご指摘ですね.オフィスビルのトイレにおいて,利用者が固定されている安心感は確かに大切な要素かもしれません.また,「トイレ用擬音装置ではなく,環境音楽を流すことで音のマスキングを」というご提案も興味深いです.高田様は,利用者同士が顔見知りである度合いと心理的な落ち着きの関係性について,どのようにお考えでしょうか.また,音のマスキングに環境音楽を活用するアイデアについて,所感をお聞かせいただけますと幸いです.
(高田様)
利用者層が固定されているという安心感は,オフィスビルのトイレならではの特性と言えるかもしれません.常連の方が多いほど,心理的な落ち着きにつながる面はあるでしょう.一方で,「いつもと違う人がトイレを使っている」状況に違和感を覚える向きもあるはず.同じオフィス内でも,フロアが変われば居心地の差を感じるという声は,私もよく耳にします.やはり個人のプライバシーに深く関わる空間だけに,安心して利用できる環境づくりは設計上の重要なポイントです.
ハード面の仕切りをしっかりと設けることはもちろん,見知らぬ人の出入りを最小限に抑える運用面の配慮も必要かもしれません.いかに「自分だけの空間」という感覚を担保できるか.利用者心理を汲み取りながら,丁寧に設えを練り上げていきたいですね.音のマスキングへの環境音楽の活用は,発想の転換を迫る興味深いご提案だと感じました.特に,用を足す際の音は,人前で発することへの心理的な抵抗感が大きい.何かしらのマスキング音が流れていれば,その負担は幾分和らぐはずです.
かといって,「トイレ用擬音装置」のようなありきたりな音では,逆に気恥ずかしさを感じてしまうことも.適度にボリュームがあって,聴いていて不快感のないBGM.空間との調和も考慮に入れながら,最適な選曲を探ってみるのは面白い試みかもしれません.心地よさの追求は,トイレ空間の設計において,これからますます重要になるファクターの一つだと思います.
(高橋)
高田様,それぞれの論点について示唆に富むお答えをいただき,誠にありがとうございます.トイレという特殊な空間だからこそ,利用者の心理状態に細やかな配慮を払うことが何より大切なのですね.プライバシー確保のためのハード・ソフト両面の工夫.利用者の居心地に直結するBGMの在り方.どちらも,快適なトイレ環境の実現に欠かせない要素として,しっかりと受け止めておきたい重要なご指摘でした.
高田様の講演からは,「利用者ニーズから考える」というスタンスの重要性を改めて教えていただいたように思います.現場の生の声に真摯に耳を傾け,フットワークの軽さを忘れずに一つひとつ課題解決に取り組んでいく.トイレ空間の進化は,そうした地道な積み重ねの先にこそ実現できるのだと実感しました.
本日は貴重なお話をありがとうございました.いただいた数々の示唆を胸に,より利用しやすいトイレ,より快適に過ごせるトイレの実現に向けて,私たちも微力を尽くしてまいります.