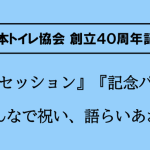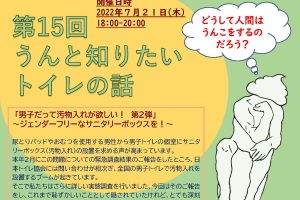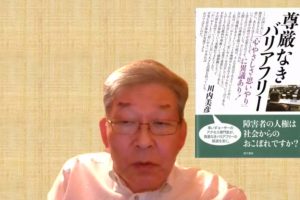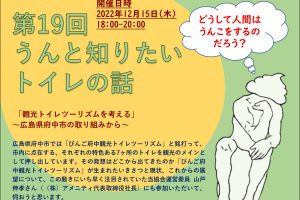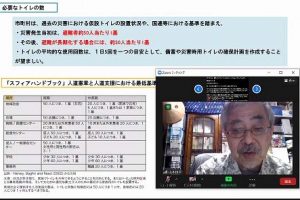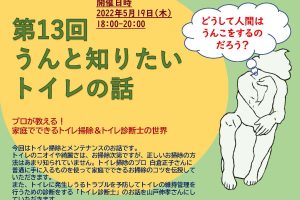司会・登壇者
- <司会>高橋未樹子(日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長)
- <登壇者>松田郁夫(石川県肢体不自由児者父母の会連合会 会長))、坂下喜美恵・熊野真由美(輪島市肢体不自由児者父母の会)
講演概要
(高橋)(司会)
第45回「うんと知りたいトイレの話」を始めていきたいと思います。今日は車椅子使用者が経験した能登半島地震ということで、石川県肢体不自由児者父母の会会長の松田さんと、輪島市で実際に地震被害に遭われた輪島市肢体不自由児者父母の会の坂下さんと熊野さんにお話を伺います。
昨年の1月1日、16時10分に震度7の地震が起こりました。地震による死者は562名で、うち災害関連死は334名になります。地震で行方不明になった方も、まだ2人いらっしゃいます。能登のほうでは、地震の後、9月にも大きな水害が起こり、16名が亡くなっています。今年4月13日にようやく指定避難所が全て閉鎖されました。ただ、一部の地域においては、インフラの復旧がまだまだ全く目処が立っていません。
(松田)
本日は皆さん、お話を聞いていただくということでご参加いただき、ありがとうございます。石川県肢体不自由児者父母の会連合会の会長をしています松田といいます。
今日は、輪島市父母の会の坂下さんと熊野さんのお二人に参加いただいています。
私自身も生まれが珠洲市なので、実家のほうには親戚が住んでいます。避難所でのトイレ事情は、一般の健常者の方でも非常に大変な状況であったので、障害のある車椅子の方にとっては、もう避難所にいられないという状況でした。
障害があるお子様だけは金沢の病院施設に移したいという要望があり、そういったお手伝いをさせていただきました。
能登半島地震の震源地は珠洲市で、最大震度7という大きな地震が起きました。
坂下さんのお宅は中規模半壊で、熊野さんは全壊となり、お二人は今、みなし仮設住宅で金沢市近郊に住んでいます。ただ、坂下さんのご主人も熊野さんご本人も、輪島塗の職人さんなので、週の半ばは輪島に行かれ、週末に帰ってきてお子さんと過ごすという生活をされています。
住家の被害は10万軒を超え、うち2万5000棟が全壊・半壊です。インフラでは、能登里山海道という一本しかない大きな道が損傷し、最初の頃は道路が隆起したり崩落したりして緊急車両も入れませんでした。
多くの方が避難生活を送られていました。石川スポーツセンターに1。5次避難所を作りましたが、最初のうちは地元を離れたくないという方が多かったそうです。
(高橋)
熊野さんのご家族構成を教えていただけますか。
(熊野)
輪島朝市通りから歩いて10分ぐらいのところに住んでいました。
4人家族で、本人と私と母と弟です。本人は肢体不自由で障害者手帳1種1級、知的障害もある30代の男性です。
輪島から30分ほどのところの福祉施設に通所していました。家庭内ではハイハイで移動し、外に行くときは車椅子や歩行器を使用していました。
(高橋)
普段、地震が起こる前のトイレはどうされていましたか。
(熊野)
自宅では、ハイハイで使いやすい高さの手すりを付けて、自分でトイレに行けていました。
危ないので見守りはしていましたが、自分でトイレには行けていました。最後はちょっと拭いてあげたり、身だしなみを整えたりしましたけど。
作業所の方は、ハイハイではなく歩行器で、介助の人が横に付いていますが、自分で行きたいときに行っていました。
(高橋)
地震があったのは元旦でしたが、どういう状況で地震に遭われたんですか。
(熊野)
元旦で家族4人集まっていました。本人がドライブ好きなので、30分ほど外にドライブしたいということで出発し、10分ぐらいしたら地震に遭いました。
スマホのアラートが鳴り、広い路肩に止めたら本震が来て、車が横転しそうになりました。目の前でおうちが崩れ、土砂が流れるのを見ました。
みんなシートベルトをしていたので安全でしたが、手に持っていたスマホは後ろのトランクに飛んでいました。
(熊野)
自宅に帰ろうとしましたが、右も左も土砂で埋まっていて、周りの住民の方も「あっちもこっちも駄目」と言っていました。
5分前に通ったところにトンネルをふさぐような石や岩が落ちていて、3分か4分違ったら、土砂のところにいたかもしれません。
(高橋)
1日目の夜はどうされたんですか。
(熊野)
輪島市三井町の旧能登三井町駅のそばで、携帯も電波が届かない場所でした。子どもの車椅子や飲み物は全然持たずに出てしまい、午後12時ぐらいまでエンジンをかけたり止めたりしていました。
地域の方が集会所を開けてストーブもつけるからと誘ってくれ、男の人たちが段差だらけのところを担いで部屋に連れて行ってくれました。
たまたま赤十字社の備蓄でマットや安眠セットがあり、地域の人が配布してくれました。
余震が続き眠れず、窓からは輪島の空が真っ赤でした。ラジオで、輪島市で火災が起きていると聞きました。
地域の方々がとても親切で、母親が横になっていると毛布を持ってきてくれ、おせち料理もみんなで食べようと分けてくれました。
みんな一緒にいてくれて、本当に助けられました。公民館の運営は近所の方たちがしてくれていたのかもしれません。
一晩目は息子と床に2人でくっついて毛布にくるまり、揺れるたびに「大丈夫だよ」と言って過ごしました。
(高橋)
公民館でのトイレについて教えていただけますか。
(熊野)
1日の夜には、ダンボール製の簡易トイレが4〜5個並べられていました。簡易トイレは女子トイレ内にはあるのですが、個室ブースの外だったので、お互い顔が見える状態でトイレをしていました。簡易トイレに被せて使う携帯トイレは、1人1回で捨てるのではなく、そのまま次の人も使うという形で、数名で使いまわしていました。
避難所の廊下は雪が入って水溜りがあり、車椅子も歩行器も持っていなかったうちの子は、水溜りの中をハイハイさせてトイレまで行くと、びしょびしょになってしまうので、ナイロン袋を借りて、人がいない時に廊下の片隅で私がガードする形でおしっこをさせ、私がトイレで捨てていました。
(高橋)
男性でもプライバシーは重要でしたね。
(熊野)
夜中だったので、廊下の片隅で私がガードし、人がいない時を見計らって「大丈夫だよ」と言ってしてもらいました。
慣れない場所でちょっとショックを受けている状況でしたが、本人なりに落ち着いて一晩を過ごしてくれました。
(高橋)
翌日は家に帰ろうとされたのですか。
(熊野)
普通は10分のところが2~3時間かかりました。道路は大行列で、時間がかかりました。
家は全壊でした。お正月はみんなでおせち料理を食べる予定だったのですが、古い方の建物はぺちゃんこになっていました。
息子が「ドライブ行きたい」と言ってくれなかったら、普通に4人いたはずの部屋でしたので、本当に不幸中の幸いでした。
その潰れた家を見て、本当に思いました。
家の前が小学校で、そこに避難所があったのですが、通路はちょっと歩くだけのスペースしかなく、トイレや移動は難しそうでした。
知り合いの人が「うちも潰れているけど、部屋があるから来れば」と言ってくれ、3日ほど泊まらせてもらいました。
ずっと泊まっていていいと言ってくれ、温かいご飯も作ってくださいました。
(高橋)
知人宅でのトイレはどうでしたか。
(熊野)
山から水を汲んできて、バケツでざっと入れたら流れました。チョロチョロっとすると流れないので、勢いよく5回ぐらいやったら成功しました。
息子は手すりがないので、私と弟と両足を抱えて座らせていました。
3日後に土砂崩れの危険地域に指定され、皆、着の身着のまま脱出しました。
坂下さんがふれあい健康センターが少し空いているからと言ってくれ、1月4日か5日頃に一緒に避難しました。
(高橋)
健康センターでのトイレ状況は?
(熊野)
1階で車椅子も1台借りられました。高齢者で足が不自由な方と同じフロアに避難させてもらいました。
車椅子トイレに連れて行くとき、私がちょうどリウマチを発症していて手に力が入らなかったので、大便の時は周りの人に手伝ってもらい、おしっこは廊下の端で、毛布で隠してビニール袋にしていました。
本人は緊張かトイレが出にくくなっていました。
(高橋)
その後は?
(熊野)
健康センターは1晩で、相談して穴水町のグループホームに移動しました。普段なら30分程度ですが、このときは5時間かかりました。
このタイミングで弟がコロナを発症し、母親も同じく感染したので、2部屋で隔離し、1週間か10日ほど避難しました。
1週間座りっぱなしだと、息子の足の筋肉が落ち、車椅子に立つのに大変になりました。
その後1。5次避難所のスポーツセンター、2次避難のホテルに移動しました。
入浴は1月下旬、金沢のホテルでようやくできました。
自衛隊の風呂もありましたが、車椅子では無理でした。15分という時間制限もありましたし、男女別々なので無理でした。
現在は金沢のみなし仮設住宅に住み、子どもは金沢の施設に行き、私は平日は輪島で仕事をし、週末は家族で過ごしています。
息子は「どうして輪島に帰れないの?」と聞きますが、明確に答えられません。
ご近所も半分以下になり、どうすべきか日々考えています。
現在のみなし仮設住宅は賃貸なので、トイレには手すりを付けられず、据置型の手すりでは狭くて介助が大変です。大人2人で介助して座らせています。
(高橋)
坂下さんの家族構成を教えていただけますか。
(坂下)
夫と娘と3人家族です。娘が車椅子と歩行器を使っています。
1キロ離れた場所に母(89歳、要介護3)が暮らしていて、弟と交代で毎日行っていました。
娘が小学校に上がるときに家の1階を全部バリアフリーにしました。
過去に震度5強の地震や停電・断水を経験していたので、水とペットボトルを用意していました。
車はシャッター付きの車庫に入れてあったら出せなかったと思います。
(高橋)
地震の時の状況は?
(坂下)
早めの夕ご飯準備中でした。娘がテーブルにつかまって立っていて椅子に座ろうという時に地震が来ました。
娘は自分でテーブルの下に入れないので、夫と私が介助してテーブルの下に入れました。
びっくりして固まって体がピンと伸びてしまい、私は娘の上に覆いかぶさりました。
私は叫んでいたそうですが、地鳴りの音だけしか覚えていません。
台所なので食器が散乱しましたが、娘のいる部屋は高い物を置かず、全部固定していたので安全でした。2階は全部倒れていました。
(高橋)
避難先は?
(坂下)
母の状況を確認後、ふれあい健康センターに避難しました。道路は亀裂や陥没、橋の隆起などで通行困難でした。
若い人たちが娘を車椅子ごと2階に運んでくれました。朝市通りが燃えていて、知り合いの安否が心配でした。
(高橋)
健康センターでのトイレは?
(坂下)
水が出ないため、若い人たちがバケツで水を運んで、流しました。そのうち運んでくる水もなくなったので、携帯トイレの使い方を教えてもらい、私も次の人に説明しました。
2階の女性用トイレは3つのうち2つが壊れ、女性トイレの1つと、多機能トイレしかありませんでした。
使えるトイレが少なく混みあっていて、娘のトイレは時間がかかるので、なるべく人がいない時にトイレに行きました。
家のトイレと手すりの位置が違い、家のトイレでは見守りだけで介助はいらなかったのが、避難所では娘は介助が必要になりました。
避難所内の移動は通路が狭く、車椅子を通す時は「すみません」と声かけしながら進みました。
食べ物は、避難所近くに家がある人が、歩いて自宅に戻り持ってきてくれてなんとかなったが、トイレが大変でした。
避難所にいた1/7時点では、避難所に仮設トイレは届いていたが、車椅子で使える仮設トイレはありませんでした。
娘はハウスダストのアレルギーがあり、食べ物の制限もありました。
私はアルコールアレルギーがあるのですが、アルコールで反応が出て救急搬送されましたが、大事に至らず、避難所に戻ることができました。
救急搬送されるときには、娘に会えるのがもしかしたら最後になるかもと思いました。
7日の朝に娘を金沢の病院に預けました。
娘は髪を伸ばしていたのですが、ハサミを借りて切って、シャワーをさせてもらいました。
娘を預けたあとは、道の駅やネットカフェ、親戚の家を泊まり歩きながら、母のグループホームを探しました。
その後も避難生活は続き、ノロウイルスが流行ってきたためふれあい健康センターには戻れず、1か月ほど転々とした後、母のグループホームが見つかりました。
(松田)
県内の状況をお話しすると、のと里山海道の損傷で必要な物資輸送が困難でした。
D-MATが最初にトイレ掃除から始めるほど衛生環境が重要でした。
仮設トイレの不足、携帯トイレの使い方が分からない問題、車椅子の家族用スペースの確保などが課題でした。
トイレの環境改善のため、教室を利用して椅子式トイレスペースを作るなどの工夫が必要でした。
トイレを我慢することで災害関連死につながるリスクもあります。
自宅のトイレでは下水管の破損により逆流するケースもありました。
地域のつながりが大きな支えになりました。
今回の地震では多くの方が里帰りで被災しており、特に悲惨な状況もありました。
事前の備蓄や訓練の重要性を改めて認識しました。
地震直後に坂下さんに今足りないものを尋ねると、「人手が足りない」とのことでした。避難所を仕切る人、携帯トイレの使い方を説明する人など、市の職員だけでは人手が足りなかったそうです。
地域のサポートと連携がとても大切です。
(高橋)
会議の終盤で自助・共助・公助(7:2:1)の重要性を強調しました。
まず自分で携帯トイレの備蓄をし、実際に使用してみることが大切です。